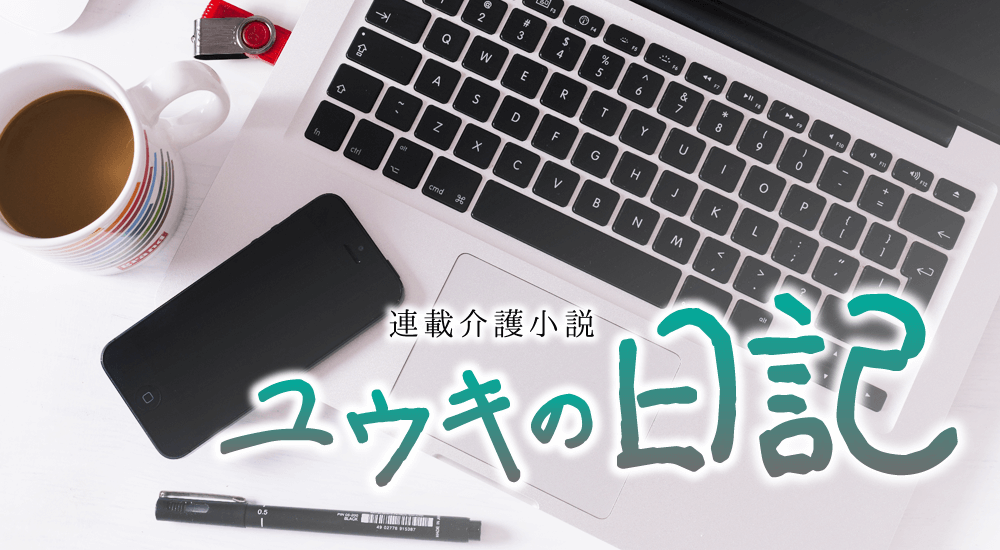第3話「いとこからの救援要請」
【前回までのあらすじ】
認知症を患った父がどのように壊れていったのか、涙ながらに語る母。
しかし有紀は「できれば聞きたくなかった」「できれば今すぐ忘れたい」と、父の現実を受け止められない。
呆然としたまま翌日の葬儀に参列すると、そこには有紀がかつてお世話になった父方の伯母・美佐子の姿が。
久方ぶりの再会に駆け寄ると、しかし彼女はどろんと濁った瞳で「あなた、どなたですか?」と言い放つのだった。
第1話「新生 アラフォー介護職」
第2話「知らなかった、父の病のすがた」
目次
脳裏にこびりつく、知らないはずの父の顔
机には次に持ち込む原稿の草案が散乱し、飲みかけのコーヒーにはカビが生えていました。
これが私の現実。親が死んでも原稿執筆。作家になるためにここまで頑張ってきたのだから!とパソコンを開いたのですが、気が付くと私は「認知症」というワードを検索していたのです。
そして改めて、自分がこの手の現実から目を背けていたのだと思い知ったのでした。
当時の私は、認知症はアルツハイマーの和名だと思い込むほどの無知でしたから、ショックを受けるというより、その膨大な内容が消化できずに胸やけを起こしてしまいました。
けれど何故か、読み止めることが出来ないのです。
そこには母が言っていた晩年の父の奇行と同じものがあったり、また母と同じように認知症患者へ心を砕けなかったことを後悔する告白もありました。どれも大変重く、深い。
それと同時に、私が今書こうとしていた「魔法と冒険の幸せファンタジー小説」が、一気にくだらないカスのような駄作に思えてきて、別の辛さも込み上げてくるのでした。
私はやり場のない怒りを亡き父にぶつけようとしました。
またお父さんのせいで私の人生はダメになった。私の夢が消えてしまった。
お父さんのせいで!お父さんのせいで!
ところが、私の脳裏には厳格で誇りに満ちた父の顔ではなく、ぼんやりと空を見つめ、まるで心が抜け落ちてたような父の顔が浮かぶのです。
私は父の晩年の顔は見ていないはずなのに。まるで目の前に佇むようにはっきりと。
いとこからの電話、そのわけは?
と、その時です。
「ジリリリリリリリリリ!!!」と、携帯から黒電話に設定していた呼び出し音が鳴り響きました。
驚いて表示を見ると、なんとそれは美佐子おばさんの娘・いとこの和子ちゃんから。
「そうか。葬儀の時、アドレスと番号を交換したんだっけ……」
あの日、入院先から駆け付けたと言って、葬儀に参加してくれた美佐子おばさんと和子ちゃん。
こちらが慌ただしくしていたせいで、最後までおばさんの病気や、そして多分「認知症」と思われる様子についても話すことはありませんでした。
ただ、私はあまりに疲れて見えた和子ちゃんの後ろ姿を黙って見送ることが出来なくて、別れ際に自分の連絡先を書いて渡したのです。
「いつでも連絡ちょうだいね。私にできることなら何でもするからね」と、その場を繕う作り笑顔を添えながら。
それが、本当に電話が掛かってくるなんて。
電話を取ると、和子ちゃんは泣いていました。そしてお酒も飲んでいるようでした。
「ごめんねえ、有ちゃん。私さあ、もう有ちゃんしか頼る人がいなくてさあ……」
思いもよらぬ転機
なんとおばさんはステージⅣの末期ガンを患っていて、もう手の施しようがないと言うのです。
で、ついに黄疸が出て動けなくなったもんだから、私が無理やり病院に連れて行ったらすい臓がんだってさ。
余命3か月。ねえ、信じられる?
しかも、お母さん病院に入ってる間にどんどん周りのことが分からなくなってっちゃって。
おじさんのお葬式でも、随分と失礼なことしてたと思うんだよね……」
「ああ、それはせん妄っていうんだよね。入院すると一時的になるんだって」
すると和子ちゃんは驚くほど甲高い声を出して私を褒めたのです。
「そ、そんなことないよ。こんなの普通だよ」
「やっぱり有ちゃんに電話してよかった。もう有ちゃんが居れば怖いものなしだよ。
これからも私たちのこと助けてくれるよね」
「えっ!?」
「実は、来週お母さんが正式に退院することになって。
その時、ケアマネさんとヘルパーさんがうちに来るんだけど、有ちゃんも同席してもらえないかな」
「ケアマネ……? ヘルパー……???」
「私ひとりじゃ心細くて。ほんと居てくれるだけでいいの。お願いします!」
私はケアマネもヘルパーも分かりませんでしたが、到底断ることのできないこの雰囲気に、美佐子おばさんの介護を手伝う約束をしてしまいました。
余命3か月。悪いとは思いながら、これくらいの期間なら恩返しをしてもいいかと思ったのもあります。
けれどこの介護生活が、3か月どころか今後の私の生活の中心になっていくのです。
「無知の知」を知った私は、この後それを後悔し落胆し怒り!そして多くを学ぶことになるのです。
【つづく】
※この作品は、登場人物のプライバシーに配慮して設定を変えていますが、私が体験した事実に基づいた物語です。